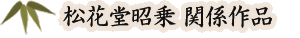| 中分類 | 工芸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小分類 | ||||||||||||
| 名称 | 松花堂好 四方釜 | |||||||||||
| 名称 よみ | しょうかどうごのみよほうがま | |||||||||||
| 作者 | 名越 三昌(古浄味) | |||||||||||
| 作者 よみ | なごしさんしょう こじょうみ | |||||||||||
| 制作年 | 江戸時代初期(17世紀) | |||||||||||
| 形態 | 釜 | |||||||||||
| 産地/発行者 | ||||||||||||
| 員数 | 1 | |||||||||||
| 法量 | 胴径13.8×高23.5 | |||||||||||
| 材質 | ||||||||||||
| 技法 | ||||||||||||
| 用途 | ||||||||||||
| 概要 | 京都名越家初代・名越三昌(桃山?江戸前期)作の「松花堂好・四方釜」である。三昌は、通称弥右衛門、剃髪して浄味と称したが、名越家は代々浄味を号するので、特に、古浄味と称する。小堀遠州・本阿弥光悦の好みの釜を造り、名工として知られている。 この釜は四方の筒形で、胴正面には「松花堂」の文字が陽鋳され、瓢箪型の環付きがつき、それぞれ「猩々翁」(本来は惺)と鋳込まれている。唐金の盛蓋が添っている。このスタイルの釜は、江戸時代初期から近年に至るまで、多くの釜師が手がけている。箱蓋表には「古浄味作 松花堂釜」と墨書きされ、裏には二代浄味が極め書きをしている。 |
|||||||||||
| 所蔵 | 収蔵庫 | |||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||
データベース上の情報および画像を無断複写・転載することは固く禁じます。